今のDAWに満足しているけど、何か新しいインスピレーションが欲しい。
そう感じているクリエイターは少なくないのではないでしょうか。私も少し前までそんなことを考えていました。約2年間愛用してきたStudio Oneの隣に、新たにBitwig Studioを導入してみた私が、まだ触り始めて大体5日間という本当に短い期間で、何に驚き、何に戸惑い、そしてどんな可能性を見出したのかをレビューしていきたいと思います。
Bitwigを購入した理由
私は元々2年ほどStudio Oneを使っています。乗り換えを検討した具体的な理由はこちらのDAW比較記事で詳しく述べていますが、端的に言うとStudio Oneの音作りのシステムに不便さを感じたからです。
なぜBitwigは「実験室」なのか
ここではなぜ私がBitwigを「実験室」だと感じたのかについて具体例を挙げながら説明していきます。
モジュレーションとルーティングの自由度
Bitwig Studioを触って、私が「これは世界が変わる」と直感的に感じた最大の理由は、音作りにおける圧倒的な自由度と、それを実現する驚くほど手軽な操作性にありました。
特にStudio Oneをずっと使ってきた私にとって衝撃的だったのは、Bitwigの代名詞とも言える「モジュレーター」です。
例えば、適当なシンセサイザーの音色を選び、LFO(周期的に動く波)のモジュレーターを一つドラッグしてみます。そして、そのLFOからシンセのフィルターカットオフ(音の明るさを調整するツマミ)に向かって、マウスで線を一本繋ぐだけ。たったこれだけの操作で、フィルターが自動でうねり始め、音が生き物のように表情を変え始めます。もちろんLFOはどのシンセにも(Studio One付属のMai Taiなどにも)ありますが、Bitwigではシンセに限らずほとんど全てのパラメータに対してこのようなモジュレーションが可能です。
この「音のパラメーターを、別の何かで操る」という感覚は、DAW上で作曲をしているというより、目の前にあるシンセサイザーのツマミをリアルタイムでいじって遊んでいるような、そんなダイレクトな体験でした。(まあハードシンセなんて触ったことないけど)
さらに、この「手軽に音を変化させる楽しさ」を加速させるのが、「Split」系のデバイス群です。これらは音を周波数帯や定位などで分割し、それぞれに全く別のエフェクトを適用できる、いわば「音の分岐装置」です。
例えば、周波数で音を分割するFreq Split。これを使った「Spectral Panner」という付属のプリセットを試してみたのですが、これが非常に面白かったです。ただ高音・中音・低音と分けるのではなく、非常に多くの帯域に複雑に分割され、それぞれが空間を飛び交うようにパンニングされることで、挿しただけでサウンドに不思議で良い感じの立体感が生まれたのには感動しました。
また、Mid-Side Splitも驚くほど手軽でした。音の真ん中(Mid)と左右の広がり(Side)の成分を瞬時に分離し、別々の処理ができる。もちろんStudio Oneでもプラグインを組み合わせれば可能ですが、ここまで直感的にできるのは大きな魅力です。
そして、こうした“分岐”の思想は、Split系以外のエフェクトの中にも及んでいます。ごく普通のリバーブですら、ウェット音(残響音)だけに別のエフェクトを追加できる「Wet FX」というセクションが標準で備わっており、リバーブの響きだけを歪ませたり、フィルターにかけたりといった、普通ならバスあセンドを使わないとできないような複雑な音作りが、デバイス一つの中で完結してしまいます。
まだ試してはいませんが、この応用で、Freq Splitを応用するとBotanicaで使われるようなSpectral Gateみたいなエフェクトも自作できるんじゃないかなどと、次から次へと実験のアイデアが湧いてきて、わくわくさせられます。
創造力を刺激する付属デバイス
DAWで音楽制作をする際、多くの場合、私たちはサードパーティ製の高機能なVSTプラグインに頼りがちです。もちろん私もそうでした。しかし、Bitwigを触り始めてから、ある大きな心境の変化が訪れました。それは、「まず付属のデバイスで試してみよう」と自然に思うようになったことです。
その理由は、Bitwigに標準で付属しているデバイス群が、単なる「おまけ」ではなく、一つ一つが個性的で、創造力を掻き立てる「主役級」のクオリティと魅力を持っているからに他なりません。
先ほど触れたSplit系のデバイスや、独創的なルーティングが可能なリバーブはもちろん、アルペジエーターやコード化といったNote FXも、まるで積み木のように組み合わせて新しいフレーズを生み出すことができます。Bitwigは音作りだけでなくフレーズ作りの面でもインスピレーションを与えてくれます。。
そして何より、これらの付属デバイスはBitwigのモジュレーションシステムと完璧に連携しています。このシームレスな統合感こそが、外部プラグインにはない大きな魅力です。
デバイスチェーンに並んだ統一感のあるビューは、見ているだけで「何か面白いことをしてやろう」という気分にさせてくれます。この「使っていて気分が上がる」という感覚的な部分も、私がBitwigのデバイスに惹かれる大きな要因なのだと思います。
結果として、Bitwigはそれ単体で「完成された音作りの遊び場」として機能しており、私を飽きさせることなく、次々と新しい実験へと誘ってくれるのです。
アイデアを止めない構造と動作
どんなに素晴らしい機能があっても、ソフトウェアの動作が重ければ、私たちの創造力はあっという間に削がれてしまいます。その点において、Bitwigは「実験室」としての役割をよく理解しているように感じました。
まず、Studio Oneと比べて、明らかにソフトウェアの起動が速いのです。 「よし、今思いついたフレーズを形にしよう」と思い立った瞬間に、ほとんど待つことなく制作画面にたどり着ける。このストレスの無さは、音楽制作のモチベーションを維持する上で、地味ながらも非常に重要なポイントです。(もちろん、これはまだ使い始めて間もないから、という可能性もあります。これから長く使っていく中でどう変化していくかは、正直なところ未知数です)
そして、この「アイデアを止めない」という思想を最も強く体現しているのが、複数のプロジェクトをタブで切り替えながら同時に開いておける、というユニークな機能です。
これは、実際に体験してみて本当に驚きました。 例えば、今作っているAという曲に行き詰まった時、過去に作ったBという曲のプロジェクトを別のタブで開き、そこから気に入っているドラムパターンやシンセの音色をコピーして、Aの曲に持ってくる、といったことが瞬時に行えるのです。
複数のプロジェクトを横断する感覚は、まるで机の上に参考書やノートを何冊も広げ、良い部分だけを切り貼りしてアイデアを練るような、アナログ的な自由さに満ちています。制作の流れを断ち切ることなくインスピレーションを再利用できるこの機能には大きな可能性を感じました。
また、インストゥルメントやFXを検索するブラウザについてもStudio Oneよりも使いやすく感じました。デバイスチェーンの+ボタンを押してインストゥルメントやFXを挿入するときに、その場所に対応したデバイスのみが出てきます。例えばインストゥルメントの後ろの+ボタンをクリックすると最初からFXに絞られてブラウザが表示されます。また、インストゥルメントやFXだけでなくプリセットも検索できるのも良いですね。特にBitwigでは独自のプリセットを作る場面も多いでしょうから。
この軽快な動作と、自由な発想を妨げないタブ式のプロジェクト管理、そして柔軟なブラウザ。これらが組み合わさることで、Bitwigは重厚な「制作スタジオ」というよりも、気軽に行って自由に遊べる「実験室」として機能します。
Studio Oneから来て戸惑ったこと
ここまでBitwigの気に入った点について述べてきましたが、やはりStudio Oneと比べて戸惑った点もあります。以下ではその部分について詳しく述べていきます。
ショートカット
まず、どんなDAWを乗り換える際にも必ず直面するのが、ショートカットキーの違いです。こればかりは、新しい環境に自分の体を慣らしていくしかありません。
しかし、一つだけえ?と思ったのが、Studio Oneでトラックのソロ/ミュートに割り当てられている「S」と「M」のキーが、Bitwigではデフォルトで機能しなかったことです。というかそもそもトラックのソロ/ミュートに対応するショートカットがデフォルトでは存在しないようです。
ですが、調べてみると、もちろんBitwigでもショートカットのカスタマイズは可能で、自分で好きなキーを割り当てられることが分かったので慣れるなりショートカットを割り当てるなりすれば問題なさそうです。
とはいえ、この「当たり前だと思っていた操作が、当たり前ではなかった」という体験は、DAWの乗り換えに伴って私の価値観を塗り替えてくれるような面白い体験でした。
デバイスビューが小さい
次に感じたのは、画面下部に表示される「デバイスビュー」の、少し窮屈な印象です。
Bitwigでは、Ableton Liveと同じように選択したトラックに挿入されているエフェクトや楽器が、横一列に並んで表示されます。全てが一つのウィンドウ内で完結しているため、画面全体の見通しが良いという大きなメリットがあるのは間違いありません。
しかし、Studio Oneのように、プラグインごとに独立した大きなウィンドウでじっくりとパラメーターを調整するのに慣れていた私にとっては、このコンパクトな表示エリアが、はじめはどうしても手狭に感じられてしまいました。
特に、多くのパラメーターを持つ複雑なシンセサイザーなどを編集する際には、「もう少し表示エリアが広ければ、もっと操作しやすいのに」と感じてしまう瞬間があったのも正直なところです。
もちろんBitwigでも拡大表示のようなオプションがありますが、DAWの設計思想の違いを感じます。全てを一画面に収めることでワークフローの速度を上げるBitwigと、一つの作業に集中するための広いスペースを提供するStudio One。この違いは、乗り換えたユーザーが最初に感じる、大きなギャップの一つかもしれません。
高い自由度 vs 学習コスト
最後に、これは戸惑いというよりも、今後の私自身課題と言った方が正しいかもしれません。それはBitwigが持つ、奥深い機能群のことです。
その代表格が、オリジナルの楽器やエフェクトをゼロから構築できるという、モジュラー環境「The Grid」です。触ってみれば、その無限の可能性はひしひしと伝わってきます。しかし、初見でこれを自由に使いこなすのは、正直なところ難易度が高いと感じました。これは、じっくりと腰を据えて学んでいくべき、巨大で魅力的な沼なのでしょう。
また、Ableton Liveのユーザーにはお馴染みで、Studio Oneでもバージョン7から追加された「クリップランチャー」も、私にとってはまだ少し慣れが必要なワークフローです。時間軸に沿ってアレンジを組み立てていくスタイルに慣れているため、ループを組み合わせて即興的に曲を展開させていくこの機能の真価は、まだ味わいきれていません。
これらの機能は、Bitwigの欠点では決してありません。むしろ、このDAWが単なる音楽制作ツールではなく、長年に渡って探求し続けられるだけの可能性を持った「実験室」であることの、何よりの証明なのだと思います。
まとめ-これからの制作スタイル
ここまで、私がBitwig Studioに初めて触れて感じた、第一印象をお話ししてきました。
その結論として、タイトルにも掲げた通り、私にとってBitwigは単なるDAWではなく、音作りやアイデア出しそのものを楽しむための「実験室」でした。手軽で強力なモジュレーションシステム、インスピレーションを刺激する付属デバイスの数々は、これからも私に多くの発見の喜びを与えてくれるでしょう。
一方で、今回の比較を通して、私が長年愛用してきたStudio Oneの魅力もまた、改めて浮き彫りになりました。
例えば作曲を強力にサポートしてくれるコードトラックや、シンプルで扱いやすいパターンエディターといった機能は、楽曲を一つの作品として堅実に組み上げていく上での、最高の「設計室」です。
この二つのDAWは、どちらが優れているという話ではなく、根本的な思想と得意分野が全く異なる、最高のパートナーになり得る存在だと、私は結論づけました。
これからは、この二つのDAWを、それぞれの得意分野を活かして使い分ける「二刀流」のスタイルで、音楽制作に臨んでいきたいと考えています。
アイデアのスケッチや、ユニークなサウンドデザインはBitwigという「実験室」で自由に楽しむ。そして、そこで生まれたフレーズや音の欠片を、Studio Oneという「設計室」に持ち帰り、楽曲として丁寧に完成させていく。
この新しい制作スタイルが、私の音楽をどのように変えてくれるのか。今から楽しみでなりません。

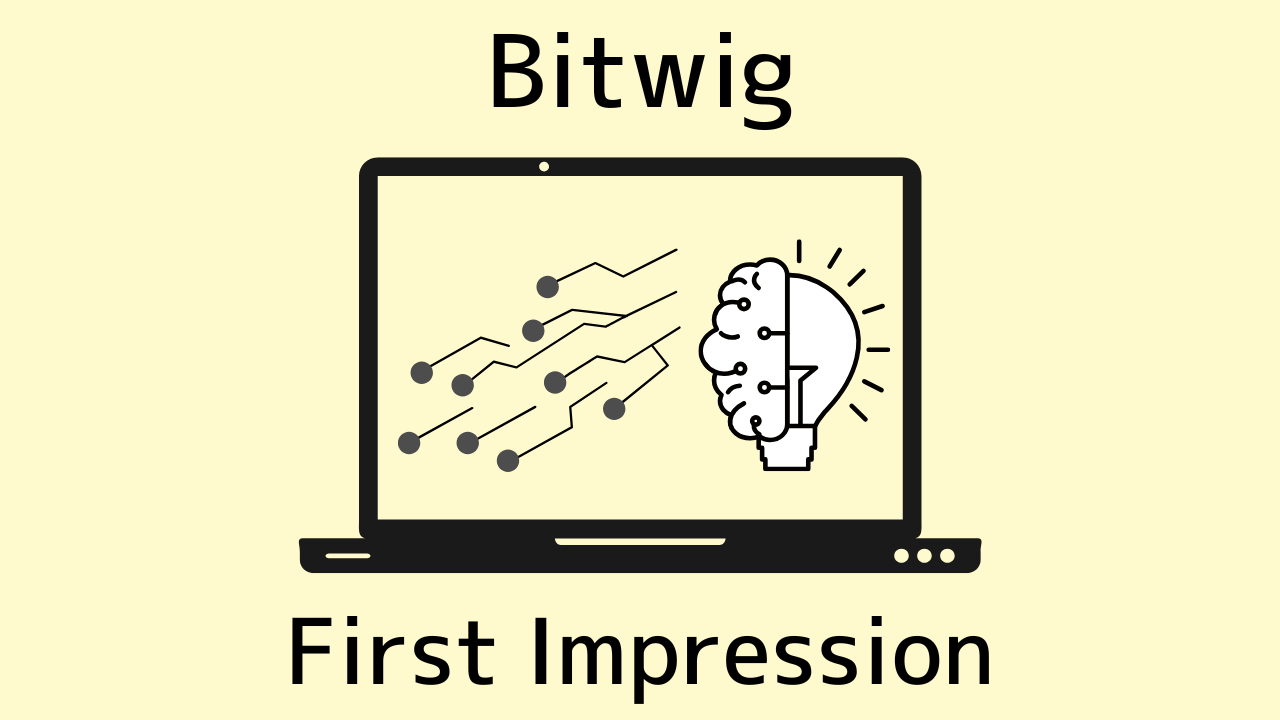




コメント